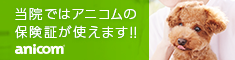雪松のお供に。
餃子の雪松が病院の近くにオープンした。
胸おどる。
だって無類のぎょうざ好きだもん。
餃子は自分で作るくらい。
でも、まあ、作るたびに、「まずい」と家族から不評を買いもするが。
まあ、そんなことはどうでもいいやね。
雪松さんに興味引かれるのはそれだけではないもんね。
だって、ここ、デジタル時代に反逆するかのような無人販売をしてるらしいし。
なんか田舎の道端でやってる農作物販売みたい。
ほのぼのするような。
そんな話題性もあってか、なんでもオープン初日は行列ができたらしい。
うむうむ。
やはり食してみたい。
無人販売で買ってみたい。
でもなあ・・・。
突然、買って帰ると、また怒られるからな。
「ちょっと、余計なもの買ってこないで。毎日、ちゃんと献立は考えてるの!」
な〜んて、ぷんぷんだもん。
それもこっぴどく。
もう。
大丈夫だって。
俺だって、ちゃんとわかってるよ。
俺、アホだけど、バカじゃないもんね。
サル並みにはちゃんと学習できるもん。
だから、そうだな。
よし、そうだ。
こうしよう。
ここは子供をだしに使おう。
帰宅後、台所にあの人がいることを確認し、呑気にテレビを見ている息子にいう。
「お前、そろそろ餃子たべたくないか」
「いらない」
「なんで?」
「だって、父さんが作る餃子、究極にまずいもん」
フン。
違うわ。
わしが作るんじゃない。
煮えくり返りそうな思いをひとまず押し殺す。
咳払いひとつ。
いうなれば、こほんとひとつ龍角散だ。
で、と。
「ちゃうで。あんな、病院の近くに餃子の雪松がオープンしたんや」
「あの無人販売の? それなら興味あるな」
「あるやろ。なら、買ってこようか」
「ええけど、ちゃんと母さんに了承得てから買ってきた方がええよ」
(あかん。ばれてる・・・)
賢明な私。
瞬時に作戦を練り直さねば。
よし。
ここは息子の機嫌をとる作戦に変更だ。
「な。受験生のお前も、たまにはちゃんとスタミナ満点の栄養食をとった方がええやろ。な、餃子食べたくなったやろ。週末にどうだ?」
「はははは」
顔をテレビに向けたまま、息子がにやりと笑います。
「かあ〜さ〜ん。父さんさぁ、オレをだしにして雪松の餃子を食べたいみたいだよ」
(こいつ、ほんまにふざけやがって。余計なこと言うなっ!)
にやにやしたむすこ。
慌てる私。
「何いうてんねん。お前を思ってのことやでぇ~。な、食べたいだろ」
「いやいや、父さんが食べたいだけだろ」
「そんなことはないぞ。きっとお前も食べたいはずだ」
「俺は、そんなに食べたくない」
あかん。
完全に心の中が読まれている。
仕方ない。
ここはいったん大人の私が素直になるしかない。
子供あいてに本気になってどうする?
「わかった。正直にいおう。食べたいのは私だ」
「素直でよろしい。じゃ、焼きで」
「なに? あほかっ!」
(ほんま、こいつ、わしのいやがることばっか言いやがって・・・。焼き餃子なんて食えるかっ!)
でもな、あかん、あかん。
冷静にだ。
そうそう。
咳払いをもう一度。
ここぞとばかりに、ゴホンとひとつ。
龍角散ダイレクトォ~!
「いいか。教えておくぞ。我が家では、餃子は水餃子。決まってるんやで」
「誰が決めたん?」
「わしが決めた」
「余計あかん。ぜぇ~ったい、焼き」
「あほ。あんな油っこいもんなんて食えるか。歳を取ったら、油より水餃子のがうまく感じんねん」
「俺は若いの。だから焼き。じゃなきゃ絶対ダメ。譲らんから」
「うるさい。水餃子だ」
「だめ。焼き。じゃなきゃほんまいらん」
「ふざけるな。餃子は水餃子だろっ! 雪松の餃子は太子の時代から水餃子。そう決まってんねん」
「なんやねん、太子の時代って」
「お前、聖徳太子もしらんのか。いい年こいて、このアホめ」
「アホはそっちやろ」
「まっ、まっ、まさか、おまえは太子が定めた十七条の憲法を読んだことないのか」
「あるかっ!」
「ふっふっふ。あの関西が生んだ偉大な人物を知らぬとは。かわいそうなエセ大阪人め」
私はにやりと息子を見下ろします。
「よろしい。おしえてやろう。まずその一、和を持って貴しとなす。うやまうことを根本とせよ」
「だ、だ、だからなんだよ」
「うやまえ。父をうやまうのじゃ。餃子は水餃子にせよ」
「あほくさ。オレ、もう、いらねえし」
そういって、息子は両手を上げて、背伸びをする始末。
くそ。
見透かしやがって。
ほんま頭にくるやつだ。
もう許さん。
今日こそ、お前に立場と言うものをはっきりさせてやる。
父親の威厳というやつだ。
お前が今まで見たことがない、ほんまもんの威厳というやつを見せつけてやろう。
いいか。
その腐り切った耳をカッポとほじって、よく聞くが良い。
「お前は大事なことを忘れている」
「何を?」
「なにを、だと。ははは。十代後半にもなってお前はまだそんなこともわからんのか」
「なんだよ」
「この家では私が絶対だ」
「はあ?」
「だから、我が家ではこの父親が絶対の権限を持っておる。幼少の頃からそう教えてきたはずだ」
私はそのまま息子を包み込むように優しい目で見つめ、ダメ押ししてやりました。
「いいか、この家では私の言うことがすべてだ。息子のお前は黙って聞け。従え!この鶴の一声に従うのだ」
「はあ? もうわけわからんし」
そう首を傾げた息子は突然、腹を抱え、くすくすと笑い出しました。
そして笑いが治らないのか、さらには噴き出しました。
だはははは。
な、なんだ、その態度は・・・。
「何がおかしい?」
「おかしいもなにも・・・」
そう言って、息子は椅子に座ったまま、上半身をくるりと回します。
台所へ顔を向けた息子は、そのまま
「かあさ〜ん、父さんが地雷踏んだで。あんなこと言っとるけど、言わせといてええんか?」
と一言。
軽率にも導火線へと火を放ったのです。
ひやあ〜。
それはあかんやつや。
絶対に使っちゃあかんやつやって!
やめろ。
我が家の最終兵器を簡単に出すな。
でも、時すでに遅し。
急いで口に手を当てるも、吐き出した言葉は戻ってきません。
あのシェーンのようにです。
馬に乗って颯爽と去っていくだけです。
振り返っても、後悔しかやって来ない。
どうやら今年もそんな夏がやってきたようです。
妻の顔つきが変わり、凍りついた我が背中に、ドライアイスのごとく、グングンと冷気が迫ってきます。
白煙と共に耳元まで一気に押し迫ると、妻はぽつりと囁くのです。
「焼きに決まってるやろ。ついでにあんたもホットプレートで踊り焼きにしたるわ」
もう、ぐうの音も出ません。
凍りついたまま、無言で項垂れている私を、息子がうれしそうに笑って言います。
「最高やな。週末は父さんの踊り焼きやて。雪松にチャーシューや!」
な、ななんてことを・・・。
これが家庭の末端に据え置かれた私の立場なのか。
ということで、今週末、我が家の夕食は雪松と一緒に脂身たっぷりの焼き豚となりました。
悲しい現実ではありますが、こうなった以上、私も受け入れるしかありません。
残された道は他にないのですから。
今週末、私は用意されたホットプレートという華やかな舞台にて、あのかつおぶしのごとく、切なく舞い、そして儚く踊り散ってまいりたいと思います。
「生きて帰らじ 望みは持たじ」
この精神一択で、今週末を過ごす所存であります。
庄内ならびに豊南町のみなさま、短い間ではございましたが、大変お世話になりました。
本当によくしていただき、今となっては感謝の言葉しかございません。
皆様方のご健康とご多幸を祈願し、これにて筆をおろしたいと思います。
世の中年男性の方々も、くれぐれもホットプレートには気をつけて、ご自愛いただければと存じます。
では、最期に。
美味しい雪松と共に。
ごめんなチャーシュー・・・。