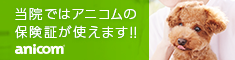少し前のこと。
浪人生の息子とテレビを見ていたら、ボートレースのCMに変わった。
レーサー同士のライバル心あり、恋愛ありの、まるで青春真っ只中を連想させるCMだ。
それを見ていて息子が言う。
「父さん、俺、たぶんボートレーサーいけんで」
「はあ?」
ニヤけやがって、このアホぼん。
受験勉強にもう飽きたのか。
いずれそうなるとは思っていたが・・・。
半ば呆れたように見ていると、当のアホウは画面の綺麗な女性にニヤついたまま、
「いやさ、前から思っていたんだけどさ、俺、ほんまボートレーサーに向いてると思うねん」だってさ。
わかったわかった。
とりあえず聞いたるわ。
「で、なんでなん?」
「前にな、部活の試合帰りに住之江でボートレースを見たことあんねん」
「お前、高校生の分際で賭けごとしてたんか?」
「ちゃうちゃう。電車の待ち時間に友達とレース見ただけ。あそこのレース場な、柵に隙間があんねん。そこから覗けるんや」
「隙間?」
「うん。こっそり覗いてるおっさん、結構おんで」
「ふーん。確かにその手のおっさんはいそうだな」
「でさ、俺も暇だから同じように覗いてた。あれ、モンキーターンっていうんやろ」
「ああ」
「俺、できると思うわ」
「ふーん」
「もしかしたらサッカーより向いてるんちゃうかな」
なんとなく言いたいことが見えてきた。
うちの息子、学校の成績はすってんころりんだった。
でも、運動ではなかなかイケていた。
幼稚園の頃、「息子さん、運動がとても得意ですね」と褒められたのが親の欲目だった。
勧められるまま体操教室に通わせた。
で、その日、いきなり8段の跳び箱を飛んでみせ、驚いた。
大鉄棒を習うと、ぐるんぐるんの大回転をすぐにできるようになった。
ロンダートやバック転もいとも簡単にこなした。
走らせても早い。泳ぎも得意だ。
球技をやりたがってサッカーを選んだが、どこのチームに入ってもそれなりの活躍をしてきた。
まあ、こやつならある程度はできるかもな。
「とにかくな。俺、思ったんや。これは俺に向いてるって」
「そうなん。でも、他にもレース系はあるだろ。競輪とかオートレースとか競馬とか」
「うーん。競輪も騎手もバイクもやってみたい。でも、ボートレースの方が自分に合ってる気がする」
「なんで?」
「ただの直感」
「ふ〜ん」
「それにな。サッカーと違って、レースは一人で戦えるやろ。誰のせいにしなくてもいいし、されないし。だから惹かれるんや」
ふーん。
なるほど、そう言うことか。
さてさて、どうしたらいいもんだか。
やりたければなら、やってみてもいいんちゃうか。
別に、みんなと同じように受験勉強なんかしなくてもいいわけだし。
受験なんてさ、下手をすれば青春という時間の無駄遣いになるからな。
と言いかけて、やっぱ、や〜めた。
子供思いの、なんとなくきれいに聞こえそうな、優しげで甘い言葉をゴックリ飲みこむ。
だって、俺、ボートレースには苦い思い出があるもんね。
あれは開業する前のこと。
開業資金の捻出をどうしようか私は本気で悩んでいた。
そんな折りに、テレビで悪いものを見てしまった。
売り場でのインタビューシーン。
「あなたは、なんでボートレースにハマったんですか」
「わし? そんなん、当たり前やろ。1レースで2000万もうけたことあんねん」
「ええ〜!!」
インタビュアーが驚いたと同時に、私も「まじか」と体を乗り出した。
ええ〜。
そうだったか。
そうかそうか。
その手があったのか。
もう銀行に頭下げて、お金借りなくてもええやん。
だははは。
悪い番組を見たもんだ。
もう、金貸しなんて糞食らえ。
遠慮なんかするもんか。
当てちまえ。
人生は一度きり。
持ち金、全部賭けてやれ。
それまでギャンブルなんてまるで興味なし。
ほとんどしたことがない。
ずぶのど素人だ。
それでも私は迷わず、週末、レース場に通い出した。
もちろん妻には内緒で。
貯めていたお金を口座からちょこまかおろし、一番近い尼崎のボートレース場へ。
当たれば、よっしゃ〜!と小躍り。
負ければ、くそっ。
ふん。
次こそ当ててやる。
鼻息荒く、賭け金を増やしていった。
高揚感からか、心臓がドキドキしていって、同時に、レースに馴染めば馴染むほど、地に足がついていないというか、ふわふわとした浮遊感を覚えるようになった。
そして次第に自分が思っていたものとは違う世界や、ギラギラとした心模様がチラついてくるようになった。
レース場は時間が進むごとに混雑してくる。
朝は閑散としていても、夕方になると一杯だ。
混雑とともに、段々と場内が荒んでいく。
響き渡る怒声。
飛び交うハズレ券。
レースが終わるたびに、一斉に券が床に投げ捨てられ、踏み潰されていく。
券売場ではずらりと並んだおっさんたちが、とんでもない賭け金を告げた。
そんなに賭けんの?
びっくりするような額を聞くたびに、自分もそれくらい賭けなければ大当たりしない気がしてきて、心がひどく乱れた。
山場になると、血走った目があちらこちらでぎらつく。
疾走する6艇のボートを凝視し、「刺さんかい、こらっ!」と声を荒げ、終われば、券を握りしめ、負けたボートレーサーを柵越しになじる。
さらなるおまけが、あれだ。
その日の最終レース。
券売場に並んでいた時のこと。
負け込んでいた。
今度こそ当てたる。
強い思いを胸に秘めて並んでいると、とつぜん、目の前を、ヨボヨボのじいさんが私を押しのけるように割り入ってきた。
なんやねん。
文句を言おうとして、言葉を飲み込む。
完全に目がイっていた。
焦点がまるで合ってない。
片側の口角からよだれが垂れている。
何かぶつぶつ呟いていて、まるで廃人だった。
驚きの眼で、凝然とじいさんを眺めていると、そのまま彼は、亡霊のように全く存在感のない足取りでふらふらと私の目前を通り過ぎていく。
そしてすぐ先の壁際の柱に立つと、もたもたとした動作でズボンとパンツを膝まで下ろした。
たるんだ下半身をためらいもせずに露出し、ぶつぶつ呟きながら、柱に向かってジョボジョボと・・・。
なのに誰も気にかけない。
賭け人たちが、券売機へ次から次へと向かい、じいさんの背後を通り過ぎていくというのに。
それどころか、じいさんのすぐ脇では、壁にもたれて座り込んだまま、レース紙に見入っている人がいた。
耳に赤ペンを挟んだその人は、紙面に目を落としたまま、ちらりとも老人を見ない。
視界にも入らないようだった。
その刹那、目に映る光景の色合いがガラリと変わった。
勝ち負けだけにこだわって、今まで気にも止めなかった景色が急に視界へと飛び込んできた。
足元にはチューハイやビール缶が転がっていた。
床には食べかけのおでんやたこ焼きの容器が捨てられている。
汁の中ではタバコの吸いがらが溢れていた。
建物の真新しさや綺麗さに誤魔化されて、そんなこと今までまるで気付かなかった。
それが突然に、周囲一帯が不衛生な空間として、退廃的に映り出すのだ。
地べたに座り込み、他会場のモニター画面を見つめ、黙々と紫煙を吹かしているおっさん。
壁にもたれて、行き交う人たちをぼんやり見回しているじいさん。
服なんてヨレヨレ。
踊り場ではへたり込んで、膝に新聞紙を拡げたまま、ぐったりと気絶したように項垂れている人もいた。
予想屋の周りには人々が群がっていて、そのすぐ近くでは陰気な顔をした男が舐めるようにお札を数えている。
どこにも笑顔なんてない。
どの顔もひどく不機嫌で、鬱屈としている。
これ、どこかで見た。
こんな退廃した空気を確かに感じたことがある。
バックパックひとつ。
「なんでも見てやれ」と学生時代、途上国のスラム街を興味本位でほっつき歩いていた時。
ガレキだらけの不衛生な街並みにはドブから腐臭がただよい、ぎらついた目の野良犬がいて、そしてあんな風に地面にへたり込む人たちがいた。
あれだ。
あれだった。
怖いもの見たさの代償で得た不意の戸惑い。
あの時以来の強烈なインパクトが湧き上がる。
いつの間にか新世界に触れる楽しさを忘れ、鬱屈とした気持ちへと迷い込み、負のスパイラルへと嵌まっていた。
これ以上、奥へ入り込むといけないかも。
途端に、喧騒が耳から消え、その場にいる自分が怖くなってきた。
真面目に働こう。
そう思うと、私はレース場をそそくさと後にし、塚口行きのバスに乗り込んだ。
阪急電車に乗って、ようやくほっとした。
そこにはいつもと同じような日常があった。
座席にはいつもの見慣れた人たちが座っていて、本を読んだり、音楽を聴いて目を閉じたり。
会話を楽しんでいる人もいた。
つり革に手をかけてぼんやり外を眺めている人たちも、いつもの街中で見かけるごく普通の人たちに見えた。
そして、そんな人々の姿がとても愛おしく思えてきた。
窓外に視線をやると、見慣れた景色が後ろ向きへと流れいく。
ぼんやりとごく普通の景色を眺めながら、時が止まったような、不毛な場所がこの世にはまだまだあるのだと改めて反芻していた。
あれ以来、私はレース場に通っていない。
もう行きたいとも思わない。
だって、私にはとても不向きな場所だとわかったから。
息子よ。
これは、たぶんの話だ。
たぶん受け取る側の感覚の問題だ。
人によって感じ方も受け取り方も違う。
でも、賭け事の世界は想像した以上に心の荒場となることがある。
軽い気持ちで踏み入れるもんじゃない。
酒と同じか。
嗜める人間ならそれでいい。
でも、その嗜み方は、人によっても、その時に置かれた心理状態によってもずいぶん変わる。
知らぬうちに、飲み込まれているなんてことはざらだ。
心身ともに麻痺し、あんなハズレ券みたいに舞い上がって。
賭ける側も、賭けられる側も。
気づけば、舞いに舞って、踊らされている。
そして散々に弄ばれた挙句、床に無惨に打ち捨てられ、気づけば靴底で踏みにじられて。
時間と金を浪費するだけで済めばいいさ。
でも、あのじいさんみたいになってどうする。
自我までどろりだ。
溶け出してからではもう遅い。
勝手な想像だろうか。
そこまで心配することはないか。
無論、杞憂であればそれでいい。
でもな。
平和で、とても呑気なお前は、私と同じような感覚に陥る気がする。
勝負師の柄ではない。
人を蹴落とすことも好みはしない。
ぎらついた目で獲物を探すタイプか。
いや、のんびり草食むタイプだろう。
だからきっと私と同じように葬られる。
ニヤけた今のその表情や心構えで、安易に手を出さないほうがいい。
なぜなら、今もまだ居着いているんだ。
私の脳裏に。
あのよだれじいさんの姿が焼き付いて離れずにいる。
脳みそに住みついたじいさんは、たるみ切った下半身をぶざまに露出したまま、あの白い壁に向かってぶつぶつと独り呟いている。
【お前は真面目に働けよ】
哀れむべきあの姿は、今も時々現れては、私のハザードランプとなって灯ってみせる。
2021年06月06日 14:36